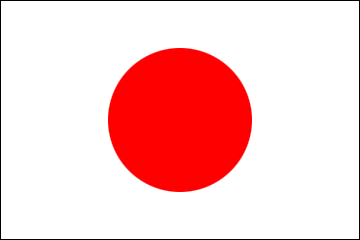カタールの歴史
平成30年9月12日
イスラム以前
英国(1973)やフランス(1976)などが行った学術調査によって、紀元前、カタール半島にも人が居住していたことが分かっています。カタールの西海岸にあるウンム・アル・マーの古墳からは、今から6千年前頃のものと思われる手斧などが発見されています。
また、ペルシャ湾はメソポタミア文明と湾岸南部やインドをつなぐ重要な水路でしたが、紀元前5世紀のギリシア人歴史家ヘロドトスは、航海にたけていたカナン人をカタールの住民としてその著書で言及しています。紀元2世紀の地理学者プトレマイオスはアラブ世界の地図に現在のカタールのズバラと思われる町を示しており、湾岸地域の重要な貿易港であったことが窺えます。
また、ペルシャ湾はメソポタミア文明と湾岸南部やインドをつなぐ重要な水路でしたが、紀元前5世紀のギリシア人歴史家ヘロドトスは、航海にたけていたカナン人をカタールの住民としてその著書で言及しています。紀元2世紀の地理学者プトレマイオスはアラブ世界の地図に現在のカタールのズバラと思われる町を示しており、湾岸地域の重要な貿易港であったことが窺えます。
イスラムの到来
 Photo: VCUQ Photo Gallary Archives
Photo: VCUQ Photo Gallary Archives
イスラムが誕生(622)した7世紀、カタール半島及びその周辺地域は、アラブ人のムンディール部族の支配下にありましたが、首長アル・ムンディール・イブン・サウィ・アル・タミームは直ちにイスラムを受容し、自分の勢力を近隣アラブ諸国に遠征したイスラム軍に参加させています。 ウマイヤ朝(661-750、ダマスカスを首都とするイスラム王朝)時代、カタールもその勢力下に入り、現在のシリア、イラクと南アラビア、インド間の交易の中継地点として、また、カタール北部に設立されたダチョウの市場により活況を呈しました。
アッバース朝(750-1258、バグダッドを首都とするイスラム王朝)時代、カタールは同王朝からの経済的支援を受け繁栄しました。カタール半島の西岸にあったMurwabフォートにはこの旨が記された碑文が残されていました。アッバース朝の衰退と共にペルシャ湾交易ルートも衰えてしまいます。 16世紀始、ポルトガル人が湾岸地域に進出してきますが、カタールは最盛期を迎えていたオスマン・トルコ(1299-1922)と提携しポルトガルを追放します。17世紀には、オランダ人が湾岸地域の支配権を確立しましたが、まもなくイギリス人がオランダ人を追放して、その後約2世紀半にわたって、同地域での絶対的優位を確立します。
アッバース朝(750-1258、バグダッドを首都とするイスラム王朝)時代、カタールは同王朝からの経済的支援を受け繁栄しました。カタール半島の西岸にあったMurwabフォートにはこの旨が記された碑文が残されていました。アッバース朝の衰退と共にペルシャ湾交易ルートも衰えてしまいます。 16世紀始、ポルトガル人が湾岸地域に進出してきますが、カタールは最盛期を迎えていたオスマン・トルコ(1299-1922)と提携しポルトガルを追放します。17世紀には、オランダ人が湾岸地域の支配権を確立しましたが、まもなくイギリス人がオランダ人を追放して、その後約2世紀半にわたって、同地域での絶対的優位を確立します。
カタールの形成
現在のカタール人の先祖は、16世紀から18世紀にかけてアラビア半島から移住してきたアラブ人です。カタールの首長家であるサーニー家も、現在のサウジアラビアの首都リヤドの北東に定住していたバニ・タミーム部族の分家とされます。 主に17世紀以降、アラビア半島内陸部ネジド地方出身のマアーディード族や同半島北西部出身のウトバ族が次々とカタールやバーレーンに移動していきました。
1762年頃、今日バーレーンの王家であるハリーファ家はカタール西部のズバラに居を構え、そこを交易及び真珠採取の拠点として栄えさせましたが、1783年、ペルシャとの抗争の末ペルシャ領だった対岸のバーレーンを掌中に収め、同地に移住し、その後もバーレーンを本拠地として現在のカタールとバーレーンで勢力を広げていきます。 その後、カタールではサーニー家がドーハを中心として勢力を伸ばし、1868年、ムハンマド・ビン・サーニーがイギリスと海上での戦争禁止を旨とする合意を結びました。これによりサーニー家はバーレーンに服属しておらず独立していると認められました。
1871年、ペルシャ湾のほかの全ての国々と同様、カタールもオスマン・トルコ帝国の影響下に入りますが、その後独立心旺盛であった第二代首長ジャーシムは、1893年にオスマン帝国がカタールに派遣した軍隊を撃退し、サーニー家の支配を確固たるものとしました。よって、現在、カタールはこの第二代首長ジャーシムを実質的な建国者とみなし、同首長が即位した12月18日を国祭日としています。ジャーシム首長はまた、オスマン・トルコの湾岸への影響力が弱まり始めると、宿敵であったアブダビのザーイド・ビン・ハリーファ首長(当時)とのホール・アル・オデイド(今日のUAEとカタールを結ぶ約23キロの回廊地帯)の領有権を巡る抗争における後ろ盾となることへの期待から、サウジのアブドルアジーズ国王と同盟関係を結び、自身もまたサウジの宗派であるワッハーブ派を受け入れました。以後、カタールは今日までワッハーブ派を受容しています。
その後、1913年には、イギリス・トルコ協定でカタールの自主権が認められ、1916年、第三代首長アブドッラーは、他の湾岸首長国と同様に、イギリスとの間に保護条約を締結、カタールはイギリスの保護下に入ることになります。 1968年1月、イギリスが財政困窮を理由に1971年までにスエズ運河以東から軍事的撤退を行うことを宣言して以来、カタールを含む9つの湾岸首長国は連邦結成の努力を続けました。しかし、1971年8月、バーレーンが単独独立を宣言したのに続き、カタールも連邦が結成された際のアブダビ首長国の優位性を嫌って、1971年9月、単独独立を宣言しました。
1762年頃、今日バーレーンの王家であるハリーファ家はカタール西部のズバラに居を構え、そこを交易及び真珠採取の拠点として栄えさせましたが、1783年、ペルシャとの抗争の末ペルシャ領だった対岸のバーレーンを掌中に収め、同地に移住し、その後もバーレーンを本拠地として現在のカタールとバーレーンで勢力を広げていきます。 その後、カタールではサーニー家がドーハを中心として勢力を伸ばし、1868年、ムハンマド・ビン・サーニーがイギリスと海上での戦争禁止を旨とする合意を結びました。これによりサーニー家はバーレーンに服属しておらず独立していると認められました。
1871年、ペルシャ湾のほかの全ての国々と同様、カタールもオスマン・トルコ帝国の影響下に入りますが、その後独立心旺盛であった第二代首長ジャーシムは、1893年にオスマン帝国がカタールに派遣した軍隊を撃退し、サーニー家の支配を確固たるものとしました。よって、現在、カタールはこの第二代首長ジャーシムを実質的な建国者とみなし、同首長が即位した12月18日を国祭日としています。ジャーシム首長はまた、オスマン・トルコの湾岸への影響力が弱まり始めると、宿敵であったアブダビのザーイド・ビン・ハリーファ首長(当時)とのホール・アル・オデイド(今日のUAEとカタールを結ぶ約23キロの回廊地帯)の領有権を巡る抗争における後ろ盾となることへの期待から、サウジのアブドルアジーズ国王と同盟関係を結び、自身もまたサウジの宗派であるワッハーブ派を受け入れました。以後、カタールは今日までワッハーブ派を受容しています。
その後、1913年には、イギリス・トルコ協定でカタールの自主権が認められ、1916年、第三代首長アブドッラーは、他の湾岸首長国と同様に、イギリスとの間に保護条約を締結、カタールはイギリスの保護下に入ることになります。 1968年1月、イギリスが財政困窮を理由に1971年までにスエズ運河以東から軍事的撤退を行うことを宣言して以来、カタールを含む9つの湾岸首長国は連邦結成の努力を続けました。しかし、1971年8月、バーレーンが単独独立を宣言したのに続き、カタールも連邦が結成された際のアブダビ首長国の優位性を嫌って、1971年9月、単独独立を宣言しました。
独立後の動き
1971年9月3日に独立を宣言したカタールは、アフマド首長を中心に国造りを始めましたが、アフマド首長の行政手腕に対する不信感が王族の間に広まり、1972年2月22日、アフマド首長の従兄弟のハリーファ・ビン・ハマド・アール・サーニーが首長の不在中にサーニー家の支持を取り付け新首長に就任しました。
ハリーファ首長は、第1次石油危機以後急増した石油収入を利用し、製鉄・肥料・石油化学などの産業基盤の建設による工業化を進め、石油枯渇後を考えての着実な工業化路線を歩む一方で、石油収入を福祉や教育面で国民に還元しました。その後、首長は、国の規模に見合った国内工業化が一応一段落したことから、国内経済の多様化(中小企業の育成及び農業・漁業の振興)や天然ガスの開発を目指しました。しかしながら、1992年以降は、ハリーファ首長の長男であるハマド皇太子(現首長)がハリーファ首長に成り代わり国政全般を取り仕切るようになり、1995年6月、ハリーファ首長の外遊中にハマド皇太子が政権奪取し、新首長に就任しました。
ハマド首長は、精力的にダイナミックな国造りを開始し、天然ガス開発、行政の合理化、民営化やカタール人優先雇用政策(カタリゼーション)を推し進めるとともに、教育やスポーツの振興、保健・医療の充実に努めています。ハマド首長は、経済面においては、天然ガス開発を中心とした開発プロジェクトを積極的に推し進めることによって経済基盤の強化を図り、政治面では、民主化を推進し、99月3月にGCC諸国で初めて女性に参政権を付与した地方自治中央評議会選挙を実施するとともに、03年4月には諮問評議会に立法権を付与することを規定した恒久基本法に対する国民投票を実施し、同基本法は05年6月に発効しました。また、ハマド首長は、青少年教育の充実を図ることがカタールの将来の国力を維持していく基礎になるとの確信の下、「教育都市」を設立し、米国・欧州の大学及び研究機関の招致に積極的に取り組むとともに、青少年のスポーツ振興にも努めました。
2013年6月25日、ハマド首長はタミーム皇太子への権限移譲を表明し、タミーム皇太子が新首長に即位しました。
ハリーファ首長は、第1次石油危機以後急増した石油収入を利用し、製鉄・肥料・石油化学などの産業基盤の建設による工業化を進め、石油枯渇後を考えての着実な工業化路線を歩む一方で、石油収入を福祉や教育面で国民に還元しました。その後、首長は、国の規模に見合った国内工業化が一応一段落したことから、国内経済の多様化(中小企業の育成及び農業・漁業の振興)や天然ガスの開発を目指しました。しかしながら、1992年以降は、ハリーファ首長の長男であるハマド皇太子(現首長)がハリーファ首長に成り代わり国政全般を取り仕切るようになり、1995年6月、ハリーファ首長の外遊中にハマド皇太子が政権奪取し、新首長に就任しました。
ハマド首長は、精力的にダイナミックな国造りを開始し、天然ガス開発、行政の合理化、民営化やカタール人優先雇用政策(カタリゼーション)を推し進めるとともに、教育やスポーツの振興、保健・医療の充実に努めています。ハマド首長は、経済面においては、天然ガス開発を中心とした開発プロジェクトを積極的に推し進めることによって経済基盤の強化を図り、政治面では、民主化を推進し、99月3月にGCC諸国で初めて女性に参政権を付与した地方自治中央評議会選挙を実施するとともに、03年4月には諮問評議会に立法権を付与することを規定した恒久基本法に対する国民投票を実施し、同基本法は05年6月に発効しました。また、ハマド首長は、青少年教育の充実を図ることがカタールの将来の国力を維持していく基礎になるとの確信の下、「教育都市」を設立し、米国・欧州の大学及び研究機関の招致に積極的に取り組むとともに、青少年のスポーツ振興にも努めました。
2013年6月25日、ハマド首長はタミーム皇太子への権限移譲を表明し、タミーム皇太子が新首長に即位しました。